将棋の優れているところは 2009/08/28

![]()
東京は若松町にアトリエS.O.Y. LABO.を構える山中祐一郎さんを訪問。静岡大学人文社会科学研究科のための授業において、わたくしと一緒に広い意味での「これからのデザインの在り方」を話してくださる方として山中さんがふさわしいと考えたからである。
山中さんのご専門は建築だが、プロダクトデザインも精力的にこなす。無印良品のプロダクトに係わり、また書物に係わる空間作り、例えば「本のための小さな家具展」や「燦架」というプロジェクトを成功に導いた異色のクリエーターだ。
そんな彼の特徴は、環境や季節と寄り添う中でデザインコンセプトを生みだしていくことにある。
そもそも彼の出発点は1995年にイギリスのDUNGENESSというまちの問題解決型の環境デザインに係わったことにはじまる。詳しくは授業の中で話すことにしたいが、極簡単に書いておくと、海流による原発を巻き込む土砂の流出、そうしてゴミ問題を「風」を利用することで一気に解決していく仕組みの提案と実践だ。
彼の目線のすばらしいところは、小さなプロダクトデザインにも、地球サイズで物事を捉える感性を忘れないことにある。
さて、履修生のみなさま、授業をお楽しみに。

【羽鳥書店 写真マップ】




◆東京は団子坂にある出版社・羽鳥書店http://www.hirano-masahiko.com/tanbou/899.htmlを表敬訪問。
千駄木の駅で降り、1番出口を出て左折。

すぐの交差点を左折して、上り坂の右側を歩く。間もなく三菱東京UFJ銀行があり、

その目と鼻の先にあるクリーニング屋さんの赤い庇が見えたらその交差点を右折。
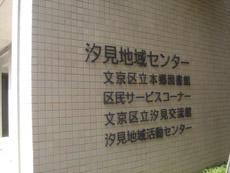
右手に汐見地域センター(文京区立本郷図書館)があり、

その道を挟んで反対側が彼羽鳥書店である。
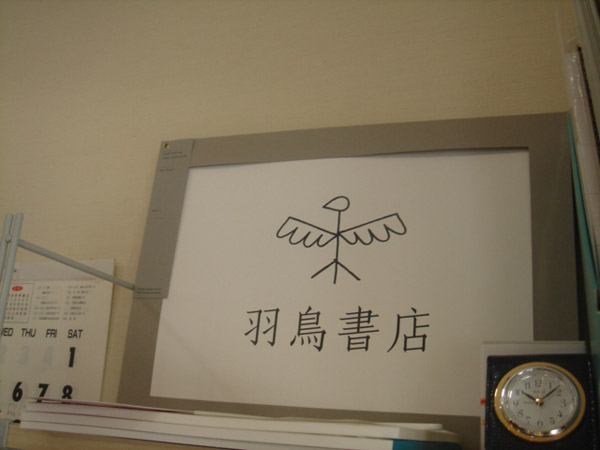
原研哉さんがプレゼンテーションされたボード。
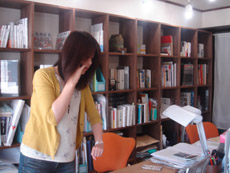
矢吹取締役はいつお会いしても、本当はメチャクチャ忙しい人だがそれを微塵も見せない。いつでもうっすらスマイルな方だ。嗚呼、こういう人になりたい(無理だけど)。
また立ち寄らせて頂きます。
![]()
◆神保町にある出版社アスペクトhttp://www.aspect.co.jp/np/index.doの編集長小村さんと打合せ。話を一気に詰めて赤提灯へ流れる(すごくいい店だった。あっ、魯迅の写真だ。わっ、林芙美子だ。うわっ・・・神保町の赤提灯には歴史がある)。そこへ島から戻ったばかりの中野純さんhttp://www.hirano-masahiko.com/tanbou/345.htmlが合流して、神田の立ち飲み屋へ移動。中野さんはNHKの番組の撮影が終わったその足で成田から駆けつけてくださった(その番組は10月4日のNHK-BSと総合で流れる予定。詳しくは日が近づいたらアップします)。楽しい時間はあっという間、中野のさんの島話にヨダレを垂らしながら、タイムアウトで後ろ手に閉まる新幹線に飛び乗る。帰りの一時間半は、アスペクト発行『本屋さんに行きたい』と青土社の新刊『建築する動物たち』を一気読み。
◆将棋がチェスよりもユニークなところは、相手からとった駒を自分の兵としても使えることだ。 手持ちの駒だけで勝負しようとするといつも同じ兵法でしか戦えなくなる。違う局面には思い切った兵法が必要だし、それが兵士のモチベーションにもつながる。
プロジェクトもまさに同じである。そもそもproject とは、pro前方(未来)に向かって + ject投げかける が語源で、それは過去の成功例という安全パイにしがみつき、手持ちの駒だけで闘うこととは逆を意味する。
同じ舟では、川は渡らない。簡単のようで人は縛られる。
![]()
バックナンバーはここ↓から。「表示件数」を「100件」に選択すると見やすくなります。