松浦寿輝の仕事

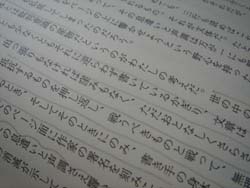
![]()
いつのことだったか。記憶というのはいつもあいまいである。いずれにしても小さな子ども時代のことだ。その日に履いていた運動靴のことだけは、妙にきちんと覚えている。父親に富士山の近く、忍野八海に連れて行かれた。そこには直径十メートルにも満たない大地の裂け目がいくつかあって、膨大な富士の湧き水がこんこんと湧き出していた。
その池の淵に立って中をのぞき込むと、その直径の長さに比べてあまりにも底の深い、そのアンバランスな自然の造形の前に足がすくんでしまったのを思い出す。全体としては常に静寂を伴っているかに見えるその池は、実は一瞬たりとも同じ状態を保っていないという現実を知ったとき、わたしは自然に対する畏怖を覚えた。
実はこの文章を小さな回想からはじめたのは、最近、わたしは、この忍野八海のような文章に出会ったからだ。この人の文章は常に静謐で、どこまでもかごやかで、終始一貫して深淵なのである。書評・批評という態度をとりながら、決して粋がらないし、小林秀雄のように凄んでみせることもしない。それでいて、云いたいことはきちんと言語化することに成功している。
その本とはRIKAさん(http://www.hirano-masahiko.com/tanbou/163.html)が送ってくださった『クロニクル』(東京大学出版会)。著者は松浦寿輝。表象文化論を分母におきながら、詩、小説、映画評論などに筆を揮う伯楽だ。
物理的な直径わずか十数センチの造本でありながら、この書評集は忍野八海のように、あまりに底が深かった。読み進めていくと、ぞっとするほど静かで、それでいて底なしだった。
松浦氏は小さな呼吸と共に吐露する。
「安定した、中庸を得た、均整の取れた「知」の姿などわたしは信じない。図書館閲覧室の机に向かう一見平穏な研究者の営みも、その内実はと言えば、数多の書物の註や書誌という命綱を頼りに、かすかな出っ張りに指を引っかけ、爪先をかけてそのつどじりじりと軀を引き上げ、頂上の見えない絶壁を禁じ登ってゆく登山家の決死の冒険の、ジグザグに折れ曲がった偏頗な軌跡でなければなるまい。波乱なく、楽々と、危なげない足取りで踏破された旅程など、そもそも踏破されるに値しなかった道程なのだ。人を不安にさせることのない「知」に、いったいどんな意味があるだろう。(「パース、アーレント、アルチュセール」より)
この知のありようはけっして忘れてはならない学問への態度であり表明である。
文中でかれがサイードを斜め読みして失敗したという小さな告白をしていたが、わたしは轍を踏まぬよう『クロニクル』を慎重に読み進めた。それがこのディスクールに対する正しい付き合い方だと、読み始めてすぐにわかったからでもある。
それから、この書物が結実した背景には、東京大学出版会のHATORIさん、YABUKIさん(http://www.hirano-masahiko.com/tanbou/88.html)がいらっしゃったことが漏れ聞こえてきた。なるほど、またこのお二人の仕業か!と妙に納得できた。そうして、あの日のような曇った陽の光の下で、もう一度忍野八海が見たくなってきた。
![]()
追記:
『クロニクル』を読んでいると、そこに紹介されている本を次から次へと手に取ってみたくなる。だが次にわたしが手に取る本はやはり松浦氏の『散歩のあいまにこんなことを考えていた』『ものの たわむれ』になりそうだ。
ちなみにわたしは『ものを考えるために散歩をしてみた』という本を出してみたい。考えるために歩くという企画だ。ソクラテスもプラトンもニーチェも西田幾多郎も、みんな歩きながら稽える達人だった。でも、やっぱり逆は成立しないだろうな、うん、わかっている。
